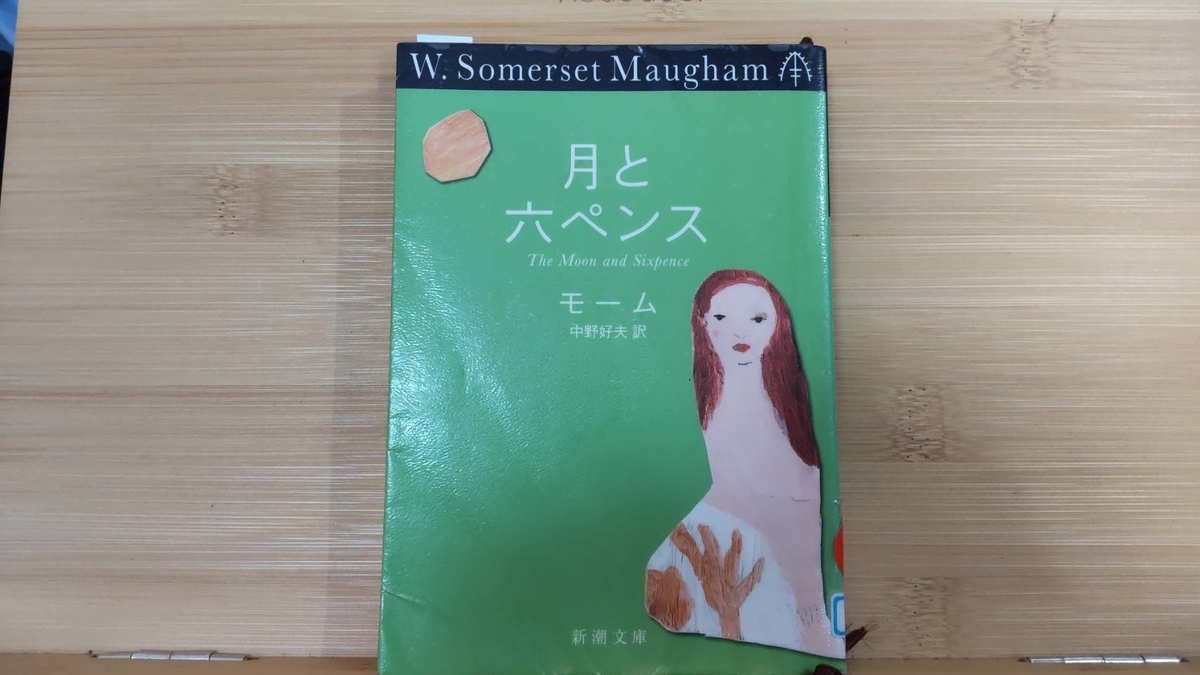
訳者の中野好夫が解説で「モームくらい安心して通俗作家だと言える作者は珍しかろう」と書いてゐる。そうなのか、モームってそんなに通俗なのか、と思って読んだみたら、想像以上に通俗でびっくりした。
中盤の「親友の妻とデキちゃう」からの「女はおかしくなって自殺する」という展開など、あきらかにエロと転落という週刊誌的好奇心をそそるように書かれてゐて、実際にそそられてグイグイ読んでしまったのだが、まあ楽しかったですよ。
「六ペンス」はそのへんの俗っぽさを象徴してゐるらしい。「月」は、主にはストリックランド(ゴーギャン)を突き動かす芸術的情熱、理想、そして「ふつうの生活」を捨てて理想に猛進する人間の不可解さ。
モームの分身たる「僕」が、ほとんど見開きごとといっていいくらいの頻度で「人間とは」「人生とは」的な箴言を吐く。この箴言がいい意味で「偉そう」な感じがしてとてもいい。前世紀の文学者はこんなふうに大上段から説教たれるみたいなことができたのだなあとしみじみ感じたことでした。
次の箇所など、素晴らしいと思う。熱い、ロマン。中野好夫も気合入ってる✨
ふらっと外国へ行ってそこに住み着いて帰って来なくなる人がときどきゐるけれど、たぶんこういうことなのだろう。
人間の中には、ちゃんとはじめから決められた故郷以外の場所に生れてくるものがあると、そんなふうに僕は考えている。なにかの拍子に、まるで別の環境の中へ送り出されることになったのだが、彼らはたえず、まだ知らぬ故郷に対してノスタルジアを感じている。
生れた土地ではかえって旅人であり、幼い日から見慣れた青葉の小道も、かつては嬉々として戯れた雑踏の町並みも、彼らにとっては旅の宿りにすぎないのだ。肉親の間においてすら、一生冷たい他人の心をもって終始するかもしれないし、また彼らが実際知っている唯一のものであるはずの風物に対してすら、ついに親しみを感ぜずじまいで終ってしまうという場合もある。
よく人々がなにか忘れがたい永遠なものを求めて、遠い、はるかな旅に出ることがあるが、おそらくこの孤独の不安がさせる業なのだろう。それとも心の奥深く根差す隔世遺伝ともいうべきものが、旅人の足を駆り立てて、遠いはるかな歴史の薄明時代の中に、彼らの祖先たちの捨てて行った国々を、ふたたび憧れ求めさせるのであろうか?
ときには漠然と感じていた神秘の故郷をうまく探ね当てることがある。それこそは求めていた憧れの故郷なのだ。そしてむろんまだ見たこともない風物の中、また見も知らぬ人々の中に、まるで生れた日以来、そこに住みつづけていたかのような心安さをおぼえる。そして、そこにはじめて休息(いこい)を見出すのだ。
355-356 改行を追加